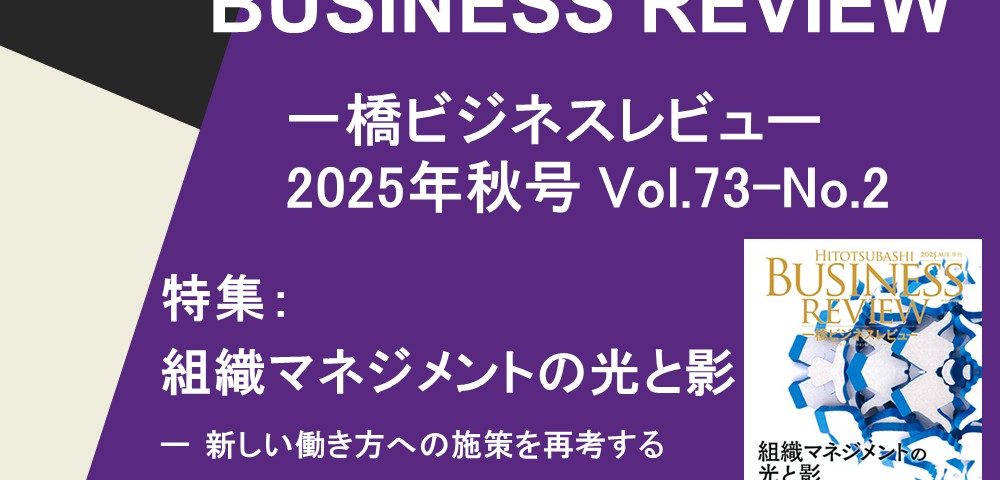2025年秋号<VOL.73 NO.2>特集:組織マネジメントの光と影 ー 新しい働き方への施策を再考する
特集:会社は従業員を守り、従業員は会社に忠誠を誓うという組織と個人の関係は、日本の組織社会において大きく変化を遂げてきた。変化の激しい市場環境に適応するため、日本企業は組織自体の変革を促し、それとともに人々の働き方も変化してきた。また、組織は社会にも従う。子育てや介護、働きがい、キャリアの重視やハラスメントへの対策など、さまざまな社会規範の変容に応じて、組織は変化を求められている。これらの変化の実現に向け、デジタル技術の活用を通じて職場や組織を変革しようとする動き(IT化・DX化)もある。このように、さまざまな変化に主体的かつ追われるように対応してきた企業にもたらされたものは光だけであろうか。光が当たる所だけを見ると、その反対側にできる影には気づきにくいものだ。本特集では、組織マネジメントの光と影の両面に焦点を当て、近年における組織と個人、それぞれの変化を改めて考察する。
特集論文Ⅰ メンタル不調からワークとライフの関係を再考する
軽部 大/内田大輔/藤田康男
(一橋大学イノベーション研究センター教授/慶應義塾大学商学部教授/株式会社Smart相談室 代表取締役・CEO)
職場におけるメンタル不調者の数は、特に新型コロナウイルス感染症の流行以降急増している。そのように職場で増加するメンタル不調の解決策として、ワークとライフの関係を見直すことが一般的に考えられがちである。しかし現実には、ワークとライフの関係を見直し、より良くすることを意図したワークライフバランス施策が、メンタル不調の解決策に寄与しているとは言い難い。ワークとライフに明確な線引きをして、過剰就労を抑制するだけでは十分ではないのである。むしろ、近年の多様な就労観と職務能力を踏まえると、より専門的で個々の従業員に即した人事施策が求められているのである。メンタル施策として考えるべきポイントは、ワークとライフのバランスの追求ではなく、多様な就労ステージとライフステージの変化に伴って誰にも起こりうるワークとライフの間のアンバランス状態を適正な状態に戻す、絶えざるリバランス施策である。
特集論文Ⅱ 集まる意味を問い直す:リモートワーク以後の関係構築とマネジメントの再設計
辰巳哲子
(リクルートワークス研究所 主任研究員)
リモートワークの定着により、働きやすさは向上した一方で、職場での関係構築や意味生成の基盤が揺らいでいる。出社回帰の動きも見られるが、重要なのは「集まり方」ではなく「集まりが意味を生む構造」をいかに設計するかである。リクルートワークス研究所が実施した「職場における集まる意味の調査」で、偶発的な対話やストーリーの共有が、信頼や一体感を支えるカギであることが示された。集まることは単なる手段ではなく、関係性を耕し、組織文化を伝える「意味のインフラ」である。今求められるのは、集まりの質を高めるマネジメントと場の再構築である。
特集論文Ⅲ あの若手はなぜ「辞めない」のか:定着か離職かの二項対立を超えて
古屋星斗
(リクルートワークス研究所 主任研究員)
働き方改革によって労働環境は改善されたが、若手社員の早期離職率はむしろ上昇している。本稿は、若手の人材育成に際して、離職率と定着率ではなく「辞めない理由」に注目し、若手が語らずにとどまっている「静かな定着(Quiet Committing)」の存在と、その戦略的意義を提起する。定着の背景にあるのは、制度や待遇の存在だけではなく、自らの成長や市場価値の実感、すなわち「キャリア安全性」である。また、定着には「稀少性」や「参照性」に基づく納得が不可欠であり、その形成にはマネジャーの育成行動や若手への越境経験の提供が重要となる。キャリア自律の時代において、企業が果たすべき役割は、「辞める理由」をなくすことではなく、「辞めない理由」を発見できる機会を提供することである。定着は結果ではなくプロセスである。
特集論文Ⅳ 組織への期待が生む不本意な在職者
吉﨑雅浩/鈴木竜太
(熊本学園大学商学部講師/神戸大学大学院経営学研究科教授)
有為な人材をいかに組織にとどめ、活躍してもらうかということが、これまでの人材マネジメントの中心的な課題であった。その一方で、不本意ながらも組織にとどまり続ける人材については、ほとんど注目されてこなかった。しかし近年は、そのような「不本意な在職者」に焦点を当てた研究が行われている。そのなかで、不本意な在職者が組織に及ぼす影響が明らかになりつつあり、マネジメント上の課題として認識されるようになってきた。本論文では、インタビュー調査のデータをもとに、特に将来の組織における仕事への期待によって不本意さを受け入れる「待望型の不本意な在職者」がいかにして生じ、変転していくのかを明らかにする。その上で、従来の日本企業の人材マネジメントが、意図せず待望型の不本意な在職者を増やし、維持し続けてきたことを指摘する。
特集論文Ⅴ 組織変革の推進と停滞のダイナミズム
砂口文兵/鈴木竜太
(神戸大学大学院経営学研究科准教授/神戸大学大学院経営学研究科教授)
社会や市場の変化に対し、企業は能動的にさまざまな変革に取り組んできた。特に昨今注目を集めるDX(デジタル・トランスフォーメーション)にかかわる変革は、組織の特定の部署だけでなく、他部署を巻き込む形で、全社的に変革が展開されることが少なくない。こうした複数の部署を巻き込む全社的な変革は、多様な変化に対応するためには不可欠である。一方で現実には、こうした全社的な変革は思いどおりに進まない場合が多い。以上のことを踏まえ、本論文では組織変革が組織に及ぼす影響に注目し、組織変革の成否をめぐるダイナミズム、すなわち組織内のさまざまな部署間で生じる相互作用が組織変革の成否とどう関係するかについて、DX化がかかわる組織変革の事例を通して検討する。
[特別寄稿]生成AIとDeepSeek:中国からの新たな競争によるグローバル・イノベーション・プラットフォーム
マイケル・A・クスマノ
(マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院教授)
生成AIは、近年急速に発展したイノベーション・プラットフォームであり、そのエコシステムは基盤モデル、インフラストラクチャ、アプリケーションの各層から構成される。OpenAI、Google、Metaなどが主要な基盤モデル提供者であり、NVIDIAがGPU市場の大部分を占めるなど、一部の企業に市場支配力が集中する傾向が見られる。さらに、数百に及ぶスタートアップがこの基盤技術の構築や改良に取り組んでおり、多くの既存企業も自社の製品、サービス、業務プロセスに生成AIを組み込む方法を模索している。そのようななかで中国のスタートアップであるDeepSeekが、基盤モデル「V3」と推論特化型モデル「R1」を発表し、業界に衝撃を与えている。驚くべきはその低コストと高性能である。本稿では、生成AIを取り巻く主要なプレイヤーと市場を概観しながら、DeepSeekの歩みと技術の本質に迫る。その上で、生成AIに関する規制やガバナンス、競争の課題などについても考える。
[連載]コンテンツビジネスから見る世界
[第4回(最終回)]ビジネスと技術、培われた人材と感性の戦略的活用
生稲史彦
(中央大学ビジネススクール教授)
[連載]ビジネス・ケースの美味しい読み方
[第2回]ビジネス・ケースを味わう:自分だけのコース料理を仕立てよう
積田淳史
(成城大学社会イノベーション学部准教授)
[連載]産業変革の起業家たち
[第24回]意志を持ってAIを活かし、幸せな働き方を実現する
平野未来
(株式会社シナモン代表取締役社長CEO)
インタビュアー:青島矢一/藤原雅俊
[ビジネス・ケース]
横浜市 ――「待機児童ゼロ」に向けた2度の挑戦
米満東一郎
(一橋大学大学院経営管理研究科イノベーションマネジメント・政策プログラム)
2013年4月、横浜市は認可保育所の「待機児童ゼロ」を達成した。2001年に国が「待機児童ゼロ作戦」を掲げて以来、全国の地方自治体が待機児童解消に取り組んでいたが、女性の就業率の上昇などに伴って保育所への入所申請者が増加し、多くの大都市において未達が続いていた。そうしたなかで横浜市が「ゼロ」を達成したことは注目を浴び、安倍首相(当時)は「横浜方式」を全国に展開することを唱え、事業手法は国の制度にも反映された。本ケースでは、横浜市が「待機児童ゼロ」を実現した経緯をたどる。なお、横浜市の「待機児童ゼロ」は、2009年以降の約3年半にわたる取り組みの成果として報道されたが、同市はそれ以前にも2003年からの3年間、時限組織を立ち上げて待機児童解消に挑んだ経緯がある。本ケースでは、それら「2度の挑戦」の関係性にも着目する。
あいや ――茶業界をグローバルな視点で革新する
軽部大/宮澤優輝/藤田源太郎
(一橋大学イノベーション研究センター教授/一橋大学大学院経営管理研究科博士課程/一橋大学商学部)
1888年に愛知県西尾市で創業した「あいや」は、近年の抹茶市場の急成長を支え、牽引してきた業界トップクラスの抹茶メーカーである。同社は1970年代初頭から抹茶を軸に置いて、伝統的な「飲む抹茶」に自らの事業領域を限定するのではなく、アイスクリームや洋菓子などの「食べる抹茶」市場を業界の先駆者として切り開いてきた。1980年代半ばから海外市場にも積極的に進出し、現在同社の売上の6割以上が海外向けである。日本の茶業界が人口減少に伴う消費量の縮小によって長期低迷してきたなかで、同社はどのように「食べる抹茶」市場を創造し、国内外で独自の地位を築くに至ったのか。本ケースでは、その具体的な過程を振り返る。同社が掲げる「抹茶を忘れず、抹茶から離れる」という考え方は、成熟業界における次の一手を考える上でも応用可能である。伝統は過去の繰り返しではなく、時代の変化とともにアップデートされるべきものである。
[マネジメント・フォーラム]
LCCの立ち上げから巨大組織のトップへ。ワクワクしながら仕事ができる組織をつくる
井上慎一
(全日本空輸株式会社代表取締役社長)
インタビュアー:米倉誠一郎
ご購入はこちらから
東洋経済新報社
URL:http://www.toyokeizai.net/shop/magazine/hitotsubashi/
〒103-8345 中央区日本橋本石町1-2-1 TEL.03-3246-5467
47巻までの「ビジネスレビュー」についての問い合わせ・ご注文は
千倉書房 〒104-0031 中央区京橋2-4-12
TEL 03-3273-3931 FAX 03-3273-7668